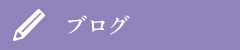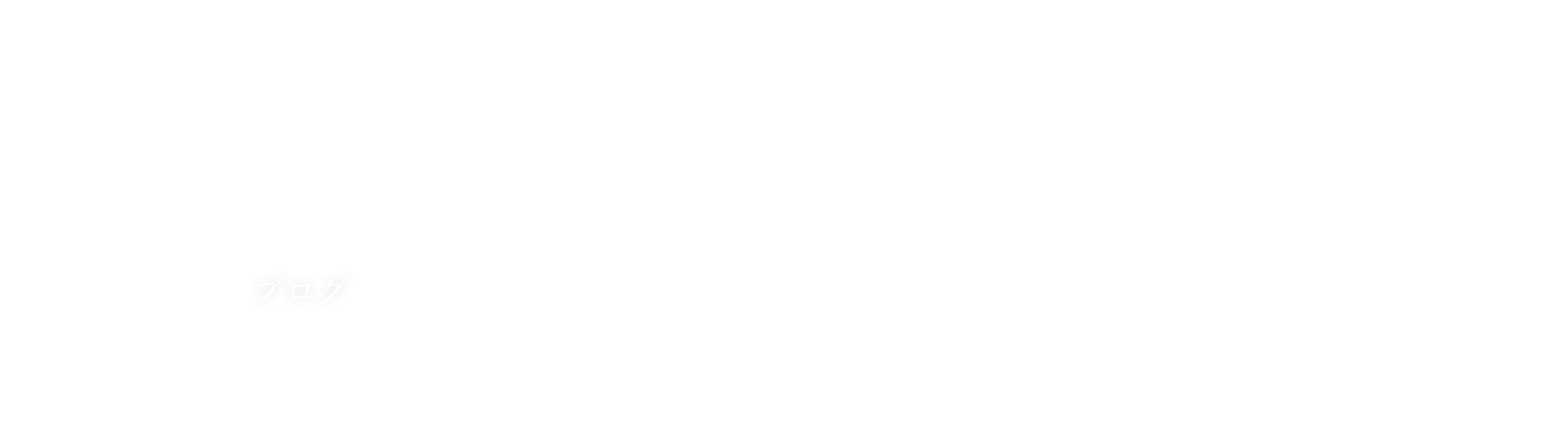
葬儀が終わった後に必要となる各種手続きや遺品整理の流れとポイント
こんにちは、青光社ブログ更新担当の岡です。
今回は、葬儀が終わった後に必要となる各種手続きや遺品整理の流れとポイントについてご紹介します。
「無事に見送ったけれど、何から始めればいいのかわからない…」と戸惑う方も多くいらっしゃいます。
心の整理と並行して行う必要があるからこそ、落ち着いて一つずつ確認していきましょう。
目次
葬儀後に必要な手続きとは?
葬儀の後、ご遺族が行うべき手続きは多岐にわたります。
法的な届け出や各種契約の解約、相続関連の準備など、期限付きのものもあるため注意が必要です。
1. 役所への届け出関係
死亡届の提出(通常は葬儀社が代行)
-
提出先:故人の住民票がある市区町村役所
-
提出期限:原則7日以内
-
必要書類:死亡診断書、届出人の印鑑など
火葬許可証の取得(葬儀社が代行)
-
火葬や埋葬のために必要な書類
-
火葬後に「埋葬許可証」として返却されます
2. 社会保険・年金・健康保険の手続き
-
国民健康保険の資格喪失届(14日以内)
-
後期高齢者医療制度の資格喪失届
-
介護保険の資格喪失届
-
年金受給停止の手続き(遺族年金へ変更手続きも)
これらはすべて役所(市区町村・年金事務所)での対応となります。
3. 金融・契約関係の整理
銀行口座の凍結と解約
故人の口座は、死亡が確認されると凍結されます。
相続手続き完了までは原則として出金ができません。
必要書類:戸籍謄本、遺言書、相続人全員の印鑑証明など
保険・クレジットカード・公共料金の解約・名義変更
-
生命保険や医療保険の請求
-
携帯電話・インターネットの解約
-
電気・ガス・水道の名義変更または解約
手続き漏れが多い項目なので、チェックリストを作って一つずつ対応するのがおすすめです。
4. 遺品整理のタイミングと注意点
葬儀後すぐに始める必要はありません。
気持ちの整理がついてから、ゆっくりと進めて構いません。
ただし、賃貸住宅に住まれていた場合など、退去期限があるケースは早めの行動が必要です。
遺品整理のポイント
-
処分前に、相続財産が含まれていないか確認(現金・通帳・貴金属など)
-
写真や手紙など思い出の品はすぐに捨てない
-
不用品は業者に依頼する方法も(遺品整理士など専門業者の利用が安心)
5. 相続関係の準備と流れ
相続は、「いつ・誰が・どのように」分けるのかを明確にすることが重要です。
-
遺言書の有無の確認(公正証書 or 自筆遺言)
-
相続人の確定(法定相続人を調査)
-
財産目録の作成(不動産・預貯金・借金など)
-
相続放棄や限定承認の検討(相続開始から3ヶ月以内)
相続税の申告が必要な場合は、10ヶ月以内に税務署へ申告・納税する必要があります。
青光社のサポート体制
青光社では、葬儀後の不安を軽減するため、以下のようなサポートも行っています。
-
行政手続きのアドバイス
-
提携する司法書士・税理士のご紹介
-
遺品整理業者の手配
-
法要や納骨のご案内
「何から手をつければいいのかわからない」という方も、どうぞお気軽にご相談ください。
まとめ
葬儀の後は、心の整理とともに、様々な実務的な作業が発生します。
事前に全体の流れを知っておくことで、気持ちにゆとりを持って対応することができます。
青光社では、葬儀前だけでなく葬儀後のサポートにも力を入れています。
「一人で抱え込まず、まずはご相談ください」
それが、私たちの想いです。
次回は、「火葬のみのシンプルプランはどんな人に向いているのか?」について解説します。
費用を抑えたい方、形式にこだわらず静かに見送りたい方に人気のスタイルです。ぜひご覧ください。